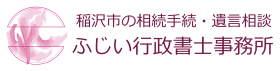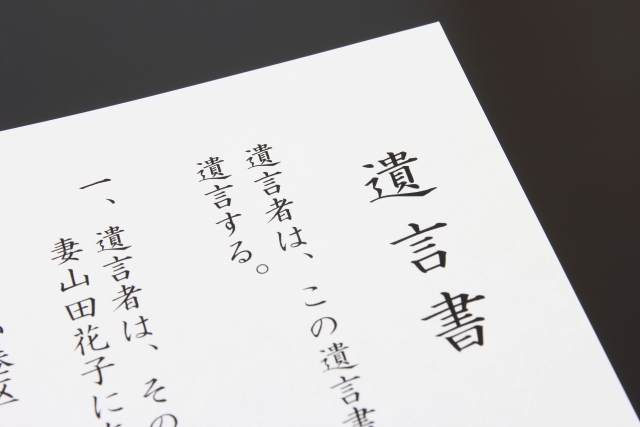

最近周りでいろいろあって・・・遺言を書いてみようかなって思ってるんだけど、何から始めればいいのかな?

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
遺言を作るお手伝いをしたり、作った遺言で実際に相続手続をする仕事をしています。
身内に不幸があったり、ご自身が病気をされたりした時に、ふと遺言を書いてみようかなと思うことありますよね。
でも、「遺言を書こうかな」なんて家族に言ったら心配されそうだし、費用はどれぐらいかかるのかなど、まずは自分で遺言について基本的なところを調べてみたいですよね。
ここでは、基本的な遺言書の種類や違いについて説明していきますよ!
【この記事の信頼性】
・遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で多くの相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
まずは遺言の種類について
遺言には次の3種類があります。
【遺言の種類】
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
秘密証書遺言はあまり見ませんので、公正証書遺言と自筆証書遺言について、詳しく説明していきます。
【公正証書遺言】とは?

こうせいしょうしょゆいごん?って何ですか?

公正証書遺言は、遺言を書く方が公証役場に行って遺言内容を伝え、公証人に作成してもらう遺言のことですよ!
遺言を作るのがご自身ではなく、公証人というところがポイントですね!
つまり、遺言の内容をご自身だけではなく、第三者(公証人や立会人)が知ることになります。
もちろん守秘義務がありますので、誰かに口外される訳ではありませんが、こっそり自宅で作る・・・という訳にはいかないのが公正証書遺言の特徴です。
(公証人が自宅等へ出張することもできます)
また、公正証書遺言の場合、公証人だけではなく、利害関係の無い立会人が2名必要となります。
「利害関係が無い」というのは、例えば相続人など財産をもらう人は立会人にはなれません。
【立会人になれない方】
①未成年者
②推定相続人
③遺贈を受ける者(相続人以外で財産をもらう方)
④推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等

ちょっと大げさかなぁ?
自分で作るのと比べてどんなメリットがあるの?

ちょっと大げさに感じるかもしれませんが、せっかく遺言を作るのなら、きちんとした形で残した方がメリットが大きいですよ!
公正証書遺言を作るメリット
①亡くなった後、家庭裁判所での検認が不要
自分で作った遺言書(自筆証書遺言)の場合、遺言者の方が亡くなった後に、相続人の方が家庭裁判所に行って、「検認」という手続きが必要になります。
自筆証書遺言では、検認を行わないと、その後の預金解約や不動産の名義変更ができません。
その点、公正証書遺言は作成の段階で公証人という第三者が関わっているため、検認という面倒な手続きが必要ありません。
そのため、公正証書遺言があれば、遺言者の方が亡くなった後すぐに、不動産や預金の名義変更が進められます。
検認について詳しくはこちらから。
遺言の検認について
②法的に有効な遺言が作成できる
「法的に有効な遺言書なんて当たり前!」と思われるかもしれませんが、自筆証書遺言の場合、実際の相続手続で無効(手続きで使えない)となるケースが多くあります。
例えば、印鑑が押してない、記載内容に不備がある・・・など、遺言書は必要な条件を満たしていないと有効と判断されずに実際の名義変更では使用できなくなってしまいます。
ご自分で書かれた遺言書の場合、条件をすべて満たしているというのはなかなか難しく、せっかく作った遺言が無効になってしまうことがあります。
この点、公正証書遺言は専門家である公証人が作るため、法的に有効な遺言書ができます。
③原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが無い
改ざん・・・だと少し物騒ですが、ご自分で書かれた遺言の場合、無くしてしまうというリスクがあります。
どこにしまったか忘れてしまうこともあると思いますし、実際の相続の際に、ご家族が見つけられない(後から出てきた)といったケースもあります。
その点、公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、遺言者の方には正本・謄本という2冊の遺言書の控えが渡されます。
そのため、紛失したり、誰かに書き換えられたといったリスクを無くすことができます。
公正証書遺言を作る際のデメリット
①作るのに費用がかかる
ご自分で作る自筆証書遺言とちがい、公証人に支払う手数料が必要となってきます。
遺言を作るのにお金がかかるというのがデメリットの一つです。
公証人に支払う手数料は財産額によって異なります。
公証人に支払う手数料について、具体的に知りたい方はこちらから。
公正証書遺言を作るための費用
②証人が2人必要
先程も少しご説明したとおり、公正証書遺言を作るには、立会人が2名必要となってきます。
しかも条件がありますので、気軽に作れる自筆証書遺言とちがい、少し形式面では手間がかかります。
立会人がいない場合は、公証役場でも準備してもらえます。

お金がかかったり、戸籍などをそろえたり・・・少し手間はかかるけど、自分で書いて無効となるぐらいなら、人生で何度も作るわけではないから、きちんとした形で遺言をのこしておくのもいいかもね。

いい面とそうでない面がありますので、ご自身に合った方法を選びましょう。
専門家に頼まなくてもご自身だけでも作れますよ。もっと具体的な手順についてもご説明しますね。
具体的な公正証書遺言の作り方を知りたい方はこちらもご参考に。
公正証書遺言の作り方
【自筆証書遺言】とは?

自分一人で遺言を作る場合についても知りたいな

それでは次はご自身で作る遺言書について説明していきますね!
【自筆証書遺言】は、遺言を書く人が自筆で作成する遺言のことです。
一人で作成できるため、家族などに内緒で作ることもできます。
民法が改正され、財産目録はパソコンでの作成がOKとなりましたが、遺言本文はすべて自筆(手書き)する必要があります。
また、訂正方法も決まっており、実際の相続でも、記載内容によっては無効となってしまう場合があります。

思ったより大変そう・・・。公正証書遺言と迷うな。

自筆で作る遺言書もメリットとデメリットがありますよ!
自筆証書遺言のメリット
①費用がかからない
紙とボールペンと、あと認印があれば書けます!
先程の公正証書遺言と比べると、お金をかけずに遺言を作ることができます。
②遺言内容の変更が簡単
公正証書遺言も訂正や変更は可能ですが、それなりに手続きが大変です。
自筆であれば、気軽に新しい遺言を作ることができます。
ちなみに、遺言は最新のものが有効となるため、過去に公正証書遺言で作っても、新たに作った自筆証書遺言が有効となります。(内容に重複がある場合)
「自筆より公正証書の方が効力が大きい!」とかはありません。
自筆証書遺言のデメリット
①全文自筆の上、訂正方法も正確に行う必要がある
手書きが面倒というのは個人的にあると思います。全文ですし・・・。
また、先程少し触れましたが、訂正方法も決まっているため、正確に行う必要があります。
自筆は気軽に作れる半面、実際の相続では本当に無効となるケースが多いので、よく調べてから作成することをお勧めします。
②亡くなった後、家庭裁判所で検認が必要な場合がある
公正証書遺言のところでも触れましたが、自筆証書遺言の場合、遺言を書いた方が亡くなった後、相続人の方が家庭裁判所に遺言を持っていって、「検認」という手続きが必要になります。
ただし、令和2年7月10日より法務局にて遺言を保管している場合は、検認不要です。
↓検認についての詳細はこちら
「遺言書の検認について」
③内容によっては無効となってしまう
自筆証書遺言の場合、有効となる条件が厳しく決まっています。
例えば、遺言を書いた日付、遺言を書いた方の名前、押印が必要といったことです。
これらの条件がすべて満たされていないと、せっかく遺言を書いても、預金の解約や不動産の名義変更ができないケースがあります。
その場合どうなるのかというと、遺言が無かった場合と同じように、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
その際、亡くなった方の遺志(どうやって分けるか?)などは反映してもいいですし、反映されない場合もあります。
④紛失や改ざんのリスクがある(発見されないリスクも)
こちらも公正証書の際に少し触れましたが、自筆だと自宅等で保管するケースが多いため、無くしたりしてしまうことがあります。
また、あまり無いですが、誰かに勝手に書き換えられるという可能性もなくはないです。
あと、実際の相続でたまにあるのが、遺産分割協議書を作る段階で、「実は遺言を発見しまして。」というケース。
途中で見つかった場合はいいですが、遺言者の方の意思に反して、遺言書が発見されない・・・という可能性もあると思います。
大事なものなので、すぐ目につくところには置いてないですしね。
余談ですが、遺言書を貸金庫に入れるのは絶対に止めましょう!
貸金庫を「開ける」のに、遺言書もしくは遺産分割協議書が必要になります。
貸金庫の中に遺言書を入れてても、作った意味ないですからね。
大事なものという意識は分かりますが、貸金庫を開けられるのはご本人だけです。

手書きするにしても何から始めればいいかな?

自筆で遺言書を作る場合の細かい手順についてはこちらをご参考に。
自筆証書遺言の作り方
お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]